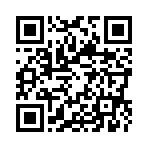2009年02月28日
【誰故草】の特徴 Ⅱ
以前に、【誰故草】の自生している環境を調べた事があるのですが、全国(西日本)の自生地に共通する点を紹介してみます。♪♪
先ずは、土壌です。♪♪
いずれも、花崗岩の風化した土壌、つまり赤土質の土壌に自生しています。♪♪痩せ地でも生育できるように進化したと思われます。♪♪
前回紹介した乾燥に対応できるのも共通するのかもしれませんね。♪♪
腐葉土などで肥えた土壌では他の植物やモグラなどに生育を阻まれてしまうんでしょうね。♪♪
次は環境です。♪♪
水はけのよさそうな斜面が多いですね。♪♪平地では育ちにくいのか自生地は残っていないようです。♪♪
人との共存をする事によって生き延びてきたのかもしれません。♪♪
従って佐賀の自生地では、保全活動として里山の維持を基本的な作業としています。♪♪
主に草刈と潅木の伐木などです。♪♪・・・刈った草は自生株のあるところからは除去します。♪♪
もう一つは、一緒に生えている植物です。♪♪
各地でそれぞれ調べてあるみたいですが、百数十種類ある内のほとんどが一致しているのには驚きでした。♪♪
ある意味で、「共生植物」と呼んでもいいかと思いました。♪♪
国の天然記念物に指定している表現が「えひめあやめ自生南限地帯」と表現されているのが何となく納得できるような気がしました。♪♪♪
最近、猪の出没が自生株を脅かしていますが、猪に限らず他の動物や植物は自然の営みの中に生育しているという観点から特別な駆除活動は、何処の管理地もされていないようです。♪♪♪
今日はこの辺で・・・。♪♪♪
先ずは、土壌です。♪♪
いずれも、花崗岩の風化した土壌、つまり赤土質の土壌に自生しています。♪♪痩せ地でも生育できるように進化したと思われます。♪♪
前回紹介した乾燥に対応できるのも共通するのかもしれませんね。♪♪
腐葉土などで肥えた土壌では他の植物やモグラなどに生育を阻まれてしまうんでしょうね。♪♪
次は環境です。♪♪
水はけのよさそうな斜面が多いですね。♪♪平地では育ちにくいのか自生地は残っていないようです。♪♪
人との共存をする事によって生き延びてきたのかもしれません。♪♪
従って佐賀の自生地では、保全活動として里山の維持を基本的な作業としています。♪♪
主に草刈と潅木の伐木などです。♪♪・・・刈った草は自生株のあるところからは除去します。♪♪
もう一つは、一緒に生えている植物です。♪♪
各地でそれぞれ調べてあるみたいですが、百数十種類ある内のほとんどが一致しているのには驚きでした。♪♪
ある意味で、「共生植物」と呼んでもいいかと思いました。♪♪
国の天然記念物に指定している表現が「えひめあやめ自生南限地帯」と表現されているのが何となく納得できるような気がしました。♪♪♪
最近、猪の出没が自生株を脅かしていますが、猪に限らず他の動物や植物は自然の営みの中に生育しているという観点から特別な駆除活動は、何処の管理地もされていないようです。♪♪♪
今日はこの辺で・・・。♪♪♪
2009年02月26日
【誰故草】の特徴
【誰故草】の特徴を少し紹介しておきます。♪♪
先ず、生えているところですが何処の自生地も里山と呼ばれる山の斜面が多いようです。♪♪
天然記念物の理由に大陸系の依存植物と説明したとおり基本的には日当たりのいい草原が自生地に適しているようです。♪♪
あやめ科のあやめ属に分類されておりますが、永い進化の末に乾燥地でも生育できる遺伝子を持っているようです。♪♪
実際佐賀の自生地でも地盤の滑落で数株犠牲になった株の根を見たことがありますが、一部で60cmを超えていたようです。♪♪
さらに根の先っぽに根瘤菌のような塊が付いていてこれが水分あるいは養分をためているのではないかと思われます。♪♪
従って、この根を切ったら栽培が出来なくなると思われます。♪♪自生株は1m以上の根が下がっているようです。♪♪
山口県の金子先生は栽培を研究されておられますが、栽培株にはこの塊は付かないとおっしゃていました。♪♪
その代わり水遣りは大切ですとも・・・。♪♪
やはり他のあやめたちと一緒で水は好むようですね。♪♪
根の進化によって乾燥地に自生できる事が最大の特徴だと思います。♪♪
花丈は10cmくらいなのに根の深さは10倍以上あるからでしょうね。♪♪
今日はこの辺で・・・。♪♪♪
先ず、生えているところですが何処の自生地も里山と呼ばれる山の斜面が多いようです。♪♪
天然記念物の理由に大陸系の依存植物と説明したとおり基本的には日当たりのいい草原が自生地に適しているようです。♪♪
あやめ科のあやめ属に分類されておりますが、永い進化の末に乾燥地でも生育できる遺伝子を持っているようです。♪♪
実際佐賀の自生地でも地盤の滑落で数株犠牲になった株の根を見たことがありますが、一部で60cmを超えていたようです。♪♪
さらに根の先っぽに根瘤菌のような塊が付いていてこれが水分あるいは養分をためているのではないかと思われます。♪♪
従って、この根を切ったら栽培が出来なくなると思われます。♪♪自生株は1m以上の根が下がっているようです。♪♪
山口県の金子先生は栽培を研究されておられますが、栽培株にはこの塊は付かないとおっしゃていました。♪♪
その代わり水遣りは大切ですとも・・・。♪♪
やはり他のあやめたちと一緒で水は好むようですね。♪♪
根の進化によって乾燥地に自生できる事が最大の特徴だと思います。♪♪
花丈は10cmくらいなのに根の深さは10倍以上あるからでしょうね。♪♪
今日はこの辺で・・・。♪♪♪
2009年02月25日
名前の由来。
【誰故草】【エヒメアヤメ】どちらが本当。??
明治32年、植物博士の牧野富太郎先生が愛媛県腰折山で発見されたこの花を新種のあやめとして発表されたのが、地名を取って【エヒメアヤメ】と命名されました。♪♪
ところが、西日本各地でもっと昔からあったことが報告され、和歌などに残っていた【誰故草】を正式名称として登録されました。♪♪
【エヒメアヤメ】は、そのまま別名として残されましたので、通称として全国で使用されています。♪♪
誰故に 乱れそめきし 花なれや
みちのしりへの 里ならなくに(西備名区)
それまでは各地で【小杜若】【一寸菖蒲】【雛菖蒲】【丘菖蒲】【姫菖蒲】【タロヘーソー】などの名前で呼ばれて居ったようです。♪♪
戦前までは小城市三日月から鳥栖・さらには筑紫野・篠栗辺りまで筑紫山系の里山には至る所で見かけられたようですが、今では佐賀県内ではここ(佐賀市久保泉町)だけにしか自生株は無いようです。♪♪
名前の通り、花丈10cm程度の可愛いあやめの花を今年も見に来て頂きたいと、町内一丸で準備しています。♪♪
郷土の歌人、中島哀浪も里山の風景を、
ふるさとの 帯隈山の うぐいすは
今も鳴くなり その竹むらに
と読んでいます。♪♪・・・・・春の里山でお逢いしましょう。♪♪♪
明治32年、植物博士の牧野富太郎先生が愛媛県腰折山で発見されたこの花を新種のあやめとして発表されたのが、地名を取って【エヒメアヤメ】と命名されました。♪♪
ところが、西日本各地でもっと昔からあったことが報告され、和歌などに残っていた【誰故草】を正式名称として登録されました。♪♪
【エヒメアヤメ】は、そのまま別名として残されましたので、通称として全国で使用されています。♪♪
誰故に 乱れそめきし 花なれや
みちのしりへの 里ならなくに(西備名区)
それまでは各地で【小杜若】【一寸菖蒲】【雛菖蒲】【丘菖蒲】【姫菖蒲】【タロヘーソー】などの名前で呼ばれて居ったようです。♪♪
戦前までは小城市三日月から鳥栖・さらには筑紫野・篠栗辺りまで筑紫山系の里山には至る所で見かけられたようですが、今では佐賀県内ではここ(佐賀市久保泉町)だけにしか自生株は無いようです。♪♪
名前の通り、花丈10cm程度の可愛いあやめの花を今年も見に来て頂きたいと、町内一丸で準備しています。♪♪
郷土の歌人、中島哀浪も里山の風景を、
ふるさとの 帯隈山の うぐいすは
今も鳴くなり その竹むらに
と読んでいます。♪♪・・・・・春の里山でお逢いしましょう。♪♪♪
2009年02月24日
【誰故草】の造花
我が町の【誰故草】(えひめあやめ)を一般公開するようになってから今年で15回目になります。♪
この間に《えひめあやめ祭り》と称して、いろいろイベントをやってきました。♪♪♪
その中の一つ。アートフラワークラブの提案で【誰故草】の造花を作って販売しています。♪
実物の栽培が難しく数も少ないというのでせめて造花で華やかさを補おうと頑張っていただきました。♪
最初のうちは実物より色も薄く形も大きかったように記憶していますが、最近はご覧のように実物とさほど変わらないほどまでに上達され、花を見慣れた私たちでもチョット見では見間違えるほどまでになりました。♪♪♪
私たちには財力が無くほとんどがボランティアで行っている保全活動の活動資金は、町内からの会費と見物された方々の浄財によって賄われております。♪♪
決して強制ではありませんが、見物にお越しの切は活動をご理解の上、ご寄付若しくは物品購入等をしていただければ助かります。♪♪♪
今年の開花予想は3月20日頃と思いますが、咲き出したらこのページで案内させて頂きたいと思っています。♪♪♪
2009年02月23日
【誰故草】(えひめあやめ)のお話
ようこそ、いらっしゃいませ。



今日は【誰故草】の話を簡単にしておきます。
現在国の天然記念物として認定されていますが特別な保護や援助は一切ありません。地元の人たちのボランティアで一切の保全活動を行っています。
天然記念物の理由は日本列島が大陸の一部であった証拠の一つであると認められたからだそうです。十数万年前何度かの氷河期に南下した動植物が日本列島が分離した時にそのまま生き残ったものだという事だそうです。
従って自生していなくては意味が無いという事です。もちろん数も少ないので珍しいものには違いありません。佐賀県の絶滅危惧種にも指定されています。
大正14年にお隣の神埼市日の隈と一緒に天然記念物の指定をされていますが、盗掘などにより日の隈は昭和37年に指定解除されています。
栽培としては地元を中心に数名の方が育てられているようですが、色々条件が揃わないと難しいらしく数はなかなか増えていないようです。
自生地では毎年僅かの開花時期に少しでも多くの方たちに可憐な花を見て頂く為に年間を通して保全活動をしています。
今年も4月4日~4月12日までの9日間《えひめあやめ祭り》として訪れる人たちをおもてなししたいと計画しておりますので、是非とも足を運んで頂き可憐な花とご対面していただきたいと思います。
現地でお待ちしております。
以上



今日は【誰故草】の話を簡単にしておきます。
現在国の天然記念物として認定されていますが特別な保護や援助は一切ありません。地元の人たちのボランティアで一切の保全活動を行っています。
天然記念物の理由は日本列島が大陸の一部であった証拠の一つであると認められたからだそうです。十数万年前何度かの氷河期に南下した動植物が日本列島が分離した時にそのまま生き残ったものだという事だそうです。
従って自生していなくては意味が無いという事です。もちろん数も少ないので珍しいものには違いありません。佐賀県の絶滅危惧種にも指定されています。
大正14年にお隣の神埼市日の隈と一緒に天然記念物の指定をされていますが、盗掘などにより日の隈は昭和37年に指定解除されています。
栽培としては地元を中心に数名の方が育てられているようですが、色々条件が揃わないと難しいらしく数はなかなか増えていないようです。
自生地では毎年僅かの開花時期に少しでも多くの方たちに可憐な花を見て頂く為に年間を通して保全活動をしています。
今年も4月4日~4月12日までの9日間《えひめあやめ祭り》として訪れる人たちをおもてなししたいと計画しておりますので、是非とも足を運んで頂き可憐な花とご対面していただきたいと思います。
現地でお待ちしております。
以上
2009年02月22日
自己紹介
佐賀市に住む草花が好きなおじさんです。

我が町の宝、国の天然記念物【誰故草】を後世に遺す為町全体で保全し少しでも多くの人に見ていただきたいと思っています。

今年も4月4日~4月12日まで《えひめあやめ祭り》としてイベントを開催して案内しますので、是非足を運んでいただき可憐な花を見ていただきたいと思います。

花の時期がソメイヨシノとほぼ同時期なので、他の時期は地域の草花を中心に書いて行けたらと思いますのでよろしくお願いします。